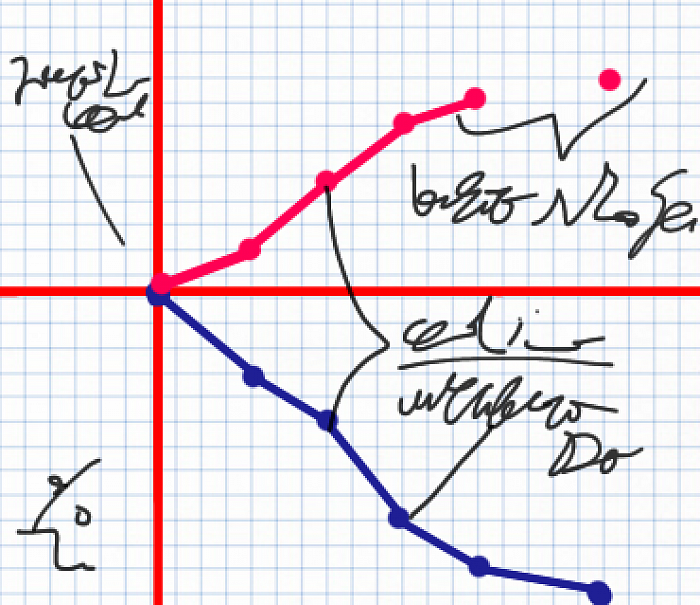専門家のインタビュー
白黒、カラー映像学者・世論明
こんにちは。司会の石本佳子です。第五弾のゲストは、白黒、カラー映像学者・与論明さんです。亡くなっている方なので、研究ノートや過去のインタビューを基にお話しさせていただきます。
プロフィール
1910年、山口県萩市の油問屋の次男に生まれた。幼い頃は野球選手志望であった。萩市市立桂萩大学を卒業した後萩市市立桂萩小学校の数学教師になった。その頃勤め先の学校の後輩教師からの勧めで人生初の動画を撮影。一時学校を退職し、イタリアへ行った。そこでルネプティ(映像作家)と組んで映画を制作。その映画は当時興行収入2位。爆発的なヒットを記録した。帰国し、再度小学校教師になる。同学校の39代目校長に就任。だが、いきなり仕事をして辞め、映像研究や映像の勉強に勤しんだ。そのころから白黒映像をカラー映像にする技術を学び始めた。二度目のイタリアへ行きルネプティと再会。白黒映像をカラー映像にし、上映。だが、時代遅れな作品だと言われ失敗に終わった。1998年に88歳で亡くなるまで、3000本に及ぶ白黒映像を手がけた。死後発表されたものも多く、チョキオークションでは与論作のビデオ一本が3億円で落札された。
白黒映像をカラー映像にする。今はカラー映像にしか人は興味がない。白黒の名作や何気ない素晴らしいビデオがカラーになることで再び人が戻ってくる。それが生きがいです。
カワヤ社インタビューより
カラー映像にも白黒映像にもそれぞれ良いことがある。カラー映像を白黒映像にすることは容易だが、白黒映像をカラー映像にするのは難しい。それをするのが私の仕事。自らの仕事に誇りを持っている。
研究ノートより
イタリアでのカラー映像にする技術は、海を渡り、与論さんによって日本という国にもたらされた。その技術は今でも有志によりすくすくと育てられている。
吉田橋次『映像史の有志』
最後まで読んでいただきありがとうございました。私も読んでいて感動してしまいました。与論さんの伝記もたくさんありますし、読んでみるととてもおもしろいです。是非読んでみてください。第六弾もお楽しみに。
(画像:フリー素材)
紙袋学者・田畑清
こんにちは。司会の石本佳子です。第四弾のゲストは、世界各国に飛び回り、講師として活躍してきた紙袋学者の田畑清さんです。田畑さんは今回の講義で、1300回目になるそうです。すごいですね!
プロフィール
1936年、奈良県生まれ。アメリカのリリチェロ大学へ留学。その後イタリアへ行き様々な学門を学んだ。そこで生涯の恩師であるサモロエア・ネミー(1889〜1961)に師事。その頃はあまり注目されていなかった紙袋学を学ぶ。帰国後、東京都立碑美大学の教授に就任。日本でも紙袋学は周りの関心がなく、こじんまりと研究を続けていた。だが数年後、イタリアの学会『メニュー学会』一行が来日。それで日本における紙袋学が注目され、田畑も大きく取り上げられるようになった。現在は奈良総合大学の学長になっており、世界中で講義をしている。著書に『紙袋の働き』、『北半球にみる紙袋反動』等がありベストセラーを記録している。
Q.紙袋学とは何ですか。
A.紙袋を有効的に使う学問。絵柄、形、サイズ、持ち手等にこだわる。
Q.こだわる理由は何ですか。
A.例えば紙袋に物を入れ、人に渡す時、相手のことを考えて、持ちやすいよう平べったい持ち手ではなく紐状のものにしたり、中身を強調するため落ち着いた色にしたりします。
Q.ではもし今わたしにプレゼントするならどういう紙袋にしますか。
A.今石本さんは緑の服を着ていらっしゃるので、被らない色にしたいですね。
Q.この学問を他に何に応用できますか。
A.ようは心づかいなので、コミュニケーションの面でも大切になってきます。
最後まで読んでいただきありがとうございました!とってもフレンドリーで話しやすい方でした。まさか紙袋とコミュニケーションが繋がるとは思いませんでした。第五弾もお楽しみに。
(画像:フリー素材)
偽背景学者・根本正蔵
こんにちは。司会の石本佳子です。第二弾に続き第三弾です!今回のゲストは、若手偽背景学者の根本正蔵さんです。
プロフィール
1995年東京生まれ。私立宮澤高等学校卒業後、『キャリア証券』に入社する前代未聞の就職を果たす。現在は、出版社『まどべ出版』の代表取締役社長に就任。若くして大企業のCEOになった男として、テレビや雑誌に何度も出演。根本は学門においても著名であり、偽背景学者として活動している。著書の『高卒・社長・学者の三つの肩書きを持つ男』はベストセラーになった。のちに大学を卒業し、現在は東京第二五大学教授に就任した。
ではお話を聞いてみましょう。
Q.偽背景学とは何ですか。
A.演劇などで、出演者の背景は絵です。絵だからこそ美しいと感じるのです。それについて研究しています。
Q.最近では新しい偽背景があると聞いたのですがどんなものですか。
A.リモートです。リモート会議などで背景をハワイなどのきれいな景色にする方は多いですよね。ですが、それはすぐに偽物だと分かります。人物の輪郭が曖昧だからです。それを見た感想を調査したりします。
Q.他にはどんな背景がありますか。
A.証明写真の背景が白かったり、ブルーバックやグリーンバックの使用時の輪郭の色など、研究は山積みです。
Q.偽背景を使ってこれからどんなことをしたいですか。
A.背景と人物による違和感の美しさを使い、映像作品を制作したいです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。偽背景学の映像作品を見てみたいですね。
第四弾もお楽しみに!
(画像:清古尊氏)
猫撫で学者・元永和美
こんにちは。司会の石本佳子です。第一弾は好評で、夢の第二弾です。今回のゲストは、猫撫で学者として知られる元永和美さんです。
プロフィール
1974年鳥取県生まれ。姉妹の長女であり、妹はシンガーソングライターのWATA。かつては政治家を目指していたが、中学生の恩師に学問の道に進むことを勧められ、勉学に励んだ。現在は、猫の撫で方を専門に研究所『cat=motonaga』を立ち上げ、日々猫と相性の良い撫で方を模索している。プライベートでは猫を2匹飼っており、動物保護団体『どうぶつずき』の運営で、動物愛護にも尽力をしている。口癖は「コマツヨイグサは多年草」。
では、お話を聞いてみましょう。
Q.猫撫で学とはなんですか。
A.猫ちゃんに気に入ってもらえる撫で方を探すことです。
Q.代表的な撫で方を教えてください。
A.首周りを撫でてあげると猫ちゃんはすごく喜びますね。
Q.高度な技を要するものもありますか。
A.ブラシやクシなどで撫でても良いですが、深すぎたら痛いし、浅過ぎたら物足りないので加減が難しいです。
Q.猫撫で学を学ぶのにはどういった理由があるのでしょうか。
A.猫は人間に癒やしを提供してくれます。その恩返しと考えてくれたらいいと思います。より良い関係を築くためにすることです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。元永さんは猫に長生きしてほしいと心を込めて撫でているそうです。
新しい発見に期待ですね。第三弾もお楽しみに!
(画像:手・リーチェ氏、猫・チェロちゃん)
紐解き学者・我孫子嘉吉
こんにちは。司会の石本佳子です。記念すべき第一弾は、紐解き学第一人者・我孫子嘉吉さんをお迎えしております
プロフィール
1958年、新潟県生まれ。新潟第三大学附属中学校の国語教論を経て、上京し、東京都立碑美大学の教授に就職。専門は物理学。現在は同大学の名誉教授になっており、私塾、我孫子塾を開塾。仕事の傍ら紐解き学の研究をしており、去年発表した論文『西日本にみる紐解き第二理論』がミリオンオルゴール論賞最優秀賞に選ばれ、世界から注目を浴びている。
では、お話を聞いてみましょう。
Q.紐解き学とはなんですか。
A.世の中には数々の種類や長さの紐があります。その紐にあった傷付けずに、かつ素早く解く技術を研究する学問です。ついになるものが紐結び学です。
Q.先生の発見した解き方にはどんなものがありますか。
A.割り箸など適当な先端の尖っていない棒などを二本用意し、隙間に差し込み、広げながら解いていきます。私どもは、『隙遠開法』と呼んでいます。
Q.一番解きにくい紐はなんですか。
A.やはり細い糸や、小さなチェーンなどです。その迅速な解き方は今模索中です。
Q.紐解き学を学ぶのにはどういった理由があるのでしょうか。
A.解けない紐は、人間に大きなストレスを及ぼします。それを解消することで、プラス57.6%の全てにおける意欲が増加することが近年のフレーム大学の研究で立証されました。それが狙いです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。我孫子教授曰く人間の脳と絡まった紐には密接な関係があるそうです。
これからの研究に期待ですね。第二弾もお楽しみに!
(画像:フリー素材)